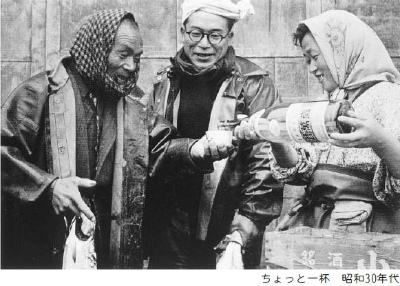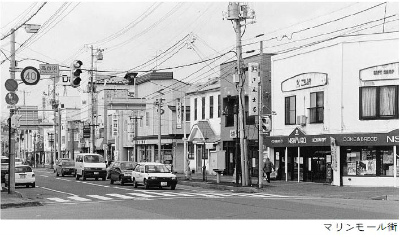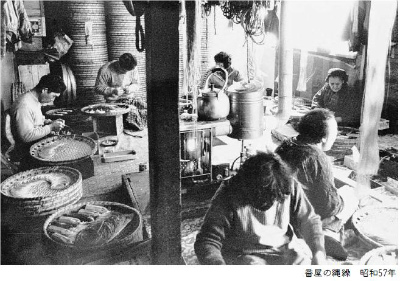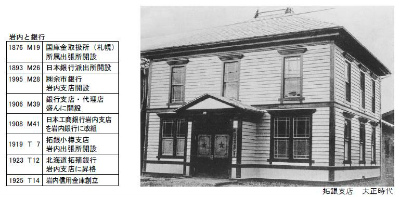共和町の三叉路、通称国富交差点に、今年も大きな雪だるまが登場しました。2月3日の朝から地元の皆さんが集まって、一日で仕上げたたようです。
というのも、私はその日朝から札幌方面へ出かけましたが、何人かの人たちが作り始めていたのを見かけました。夕方に帰ってくる時には、すでに完成していたのです。
今年で30回目の制作になるとのこと。交通事故がきっかけで作られるようになった巨大雪だるま。第一回目から通しで作られている人はいるのでしょうか。
名前は、雪だるまではなく、「安全太郎」ですよ。ちゃんと覚えてあげてくださいね。先週、降雪が少なかったので、例年に比べれば少し白さに欠けますが、皆さんの安全を見守る力は一緒です。