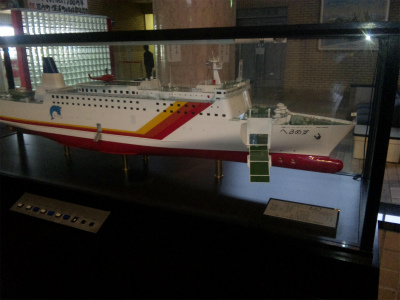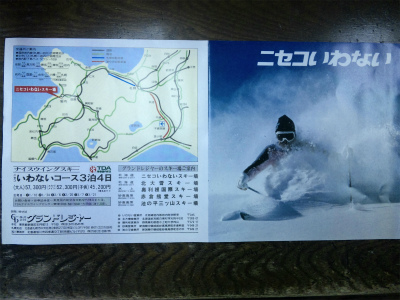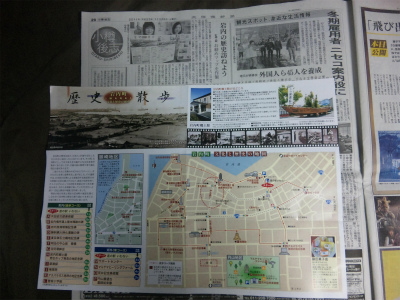写真は、岩内の地場産業サポートセンター裏手にある、町の雪捨て場です。ここには、町道から排雪された雪を積んだダンプカーや一般の事業所などから雪を積んだトラックがやって、雪を降ろします。
ここには、常時キャタピラーをつけたブルドーザーが待機していて、降ろされた雪を上手に踏み固めながら山を作っていきます。まだシーズンが始まったばかりなので、雪山にはなっていませんが、ドカ雪が降るとダンプカーは途切れなくやって来るので、どんどん雪山は大きくなっていきます。
後ろは海です。まだ海が見えますが、なぜ海に直接捨てないのか?と思いますよね。白い雪も融けるとかなり汚れています。ゴミも結構紛れているので、もしも海に雪を捨てるとシーズンが終わると、かなりのゴミが海の中にあるという状況になります。
雪捨て場も、どこでもいい訳ではなく、雪が融けるとその排水によって、近隣に迷惑を及ぼさないかなどを考えられます。よって、海のすぐ近くの広い土地が選ばれると思います。専門家のみなさん、この考え方でいいのですよね?
雪国の皆さんにとっては、当たり前の話題で申し訳ありません。この除雪、排雪ということは、雪国にとって経済的に非常に重要な位置を占めています。子供にとっても、ばあちゃんの家の雪かきをすることによって、お駄賃をもらえるのですから・・・