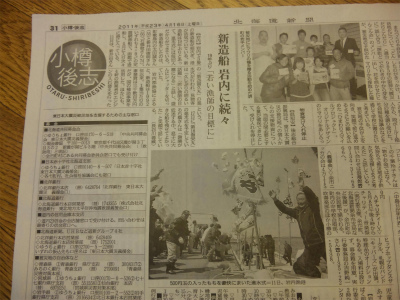岩内町と蘭越町を結ぶ道道岩内洞爺線、通称ニセコパノラマラインは9日15時に通行止め解除となりました。連休前に一度開通になったのですが、気温が低く積雪になったとのことで5月2日に通行止めになってしまいました。それが再度開通となったわけです。
写真は5月8日日曜日に撮ったものです。ここがどこか地元の方ならすぐおわかりでしょう。チーズ工場の前にある電光掲示板です。ここまで来て、あれっ?といった感じで引き返していく車がありました。
観光の面から考えると、この道はニセコから回ってくる人、積丹半島からニセコへ抜ける道へと重要なルートになっています。岩内平野を見渡すことができ、夜は夜景がきれいに見ることができます。四季折々の景色が美しい神仙沼もあります。
積丹、ニセコへの観光をお考えの方はぜひこのニセコパノラマラインを使って岩内にお立ちよりください。残雪と新緑前の白樺が美しい別世界へ。