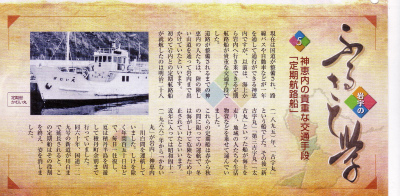岩内の市場の隣では、写真のようにテトラポットが作られています。工事の看板を見ると、泊港の補修のため?とか書いてあったような。
これは、海岸の波のエネルギーを少なくする、浸食防止などのために作られるものですね。巨大なものであるため、この埠頭で造り、船で現場に運ぶということでしょう。
青空の元、白いテトラポットが並ぶ姿はなかなか綺麗ですが、ふと考えることがあります。いろんな技術が発展しているのに、このテトラポットは私が子供の頃から同じ形で存在して、なくなっていない。これが本当に海にやさしい存在なのだろうか?
磯焼けが著しい日本海。その原因は生活排水や魚のえさとなるプランクトン、すなわち有機物の不足だと思いますが、コンクリートで海岸を必要以上に固めるというのはそろそろ考えてもいい頃なのではと思います。じゃ、どうすればいいのか?と問われれば、明確に返答することはできませんが・・・